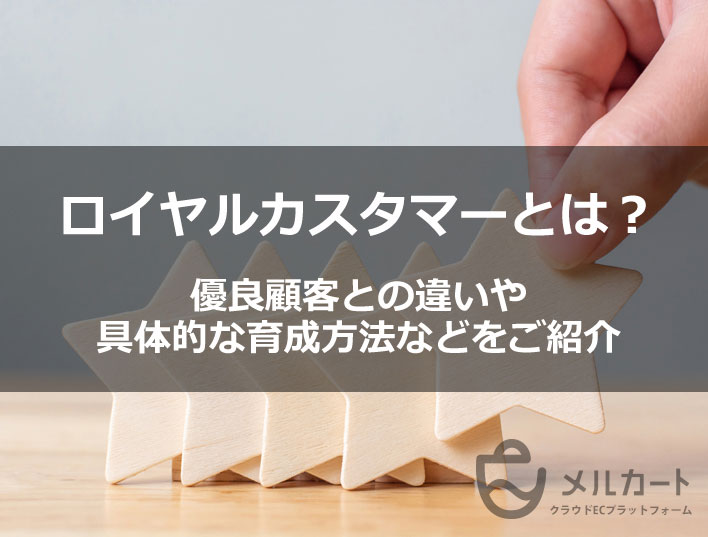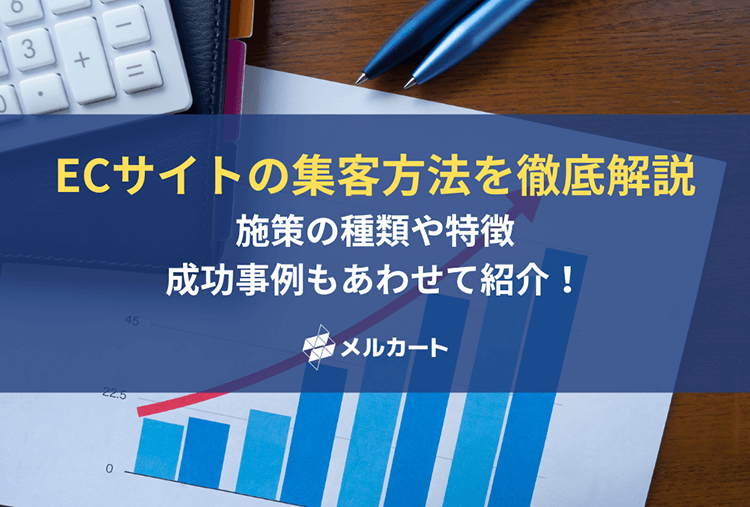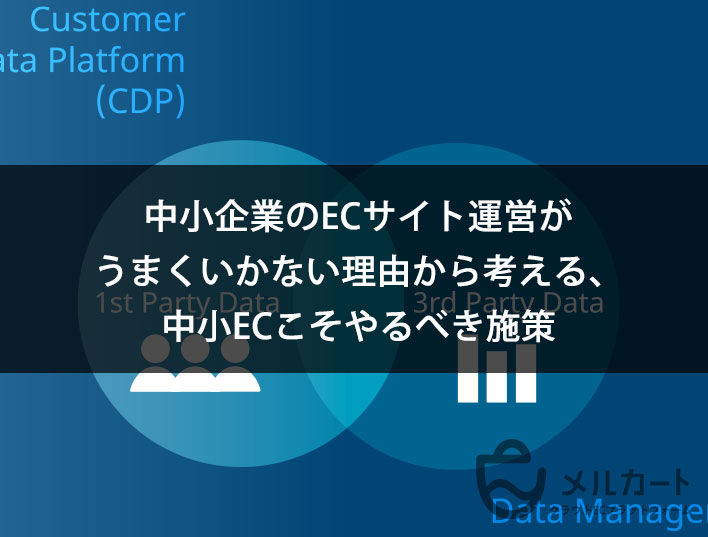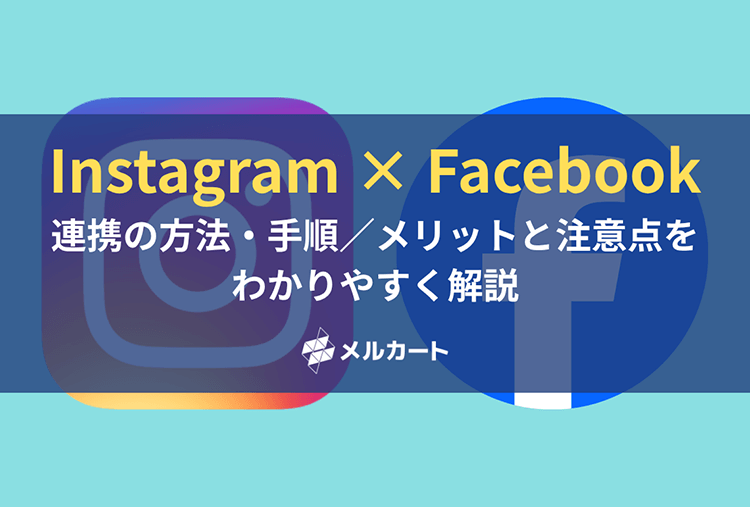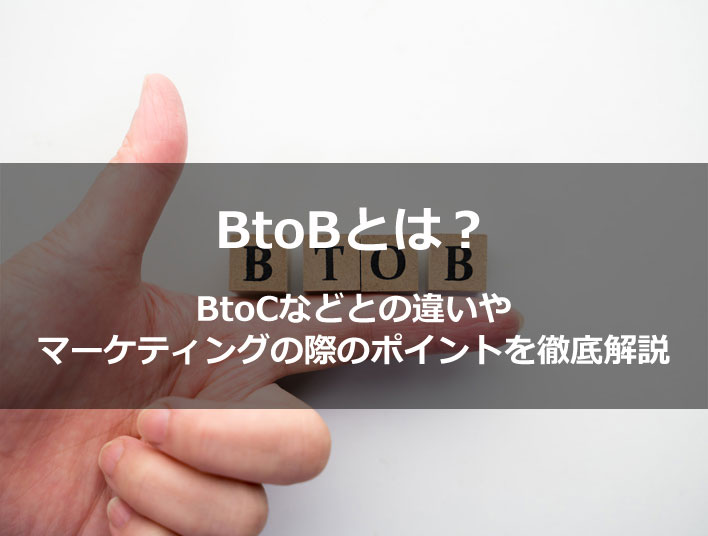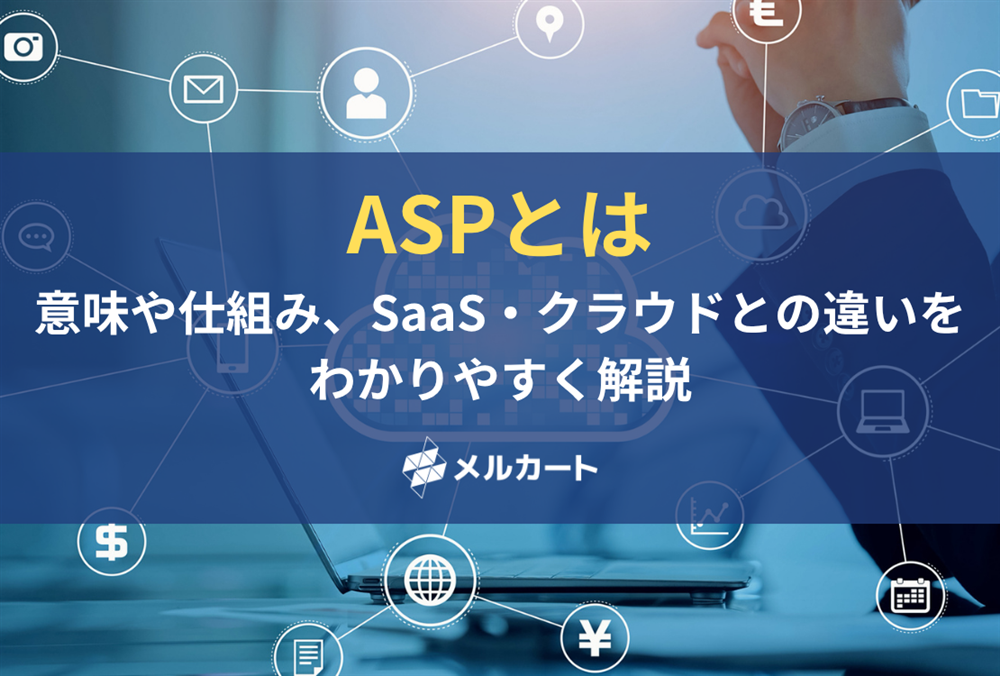EC情報メディア詳細
ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは?優良顧客との違いや育成の方法・事例を紹介!
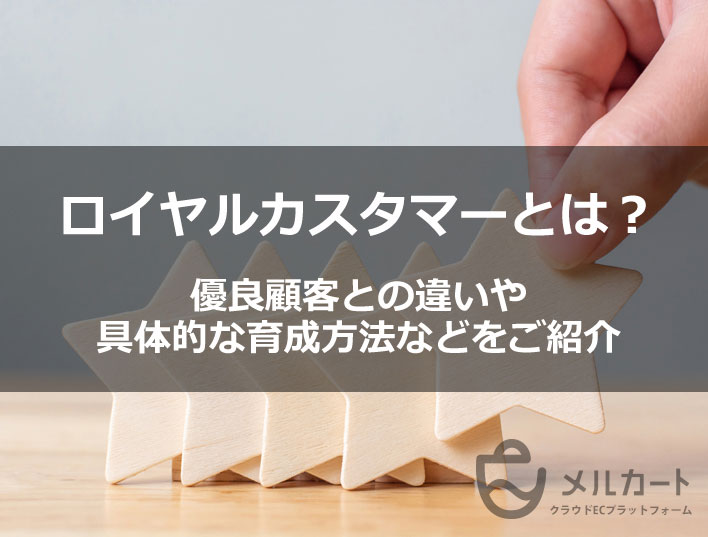
企業が事業の安定や持続的な成長を図るには、顧客と良好な関係性を築いていくことが重要です。
とくに、ロイヤルカスタマーの育成は企業にとって大切な取り組みだと言えます。
一方で、
「ロイヤルカスタマーの定義や優良顧客との違いは?」
「ロイヤルカスタマーはなぜ重要なの?」
「ロイヤルカスタマーを育てるには?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、ロイヤルカスタマーとは何なのか、優良顧客との違いやロイヤルカスタマーの育成において重要な分析の方法、育成のポイントなどをわかりやすく解説します。
ロイヤルカスタマーの育成に役立つサービスや事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
リピート購入を増やしたい方は必見!
マンガでわかるECサイトリピーター獲得の法則!
ECサイトでリピーターを獲得するための法則をわかりやすく解説したマンガです。
こんな人におすすめ
・ファン・リピーターを増やしたい
・広告費をかけずに売り上げUPをしたい
・顧客管理システムってなに?
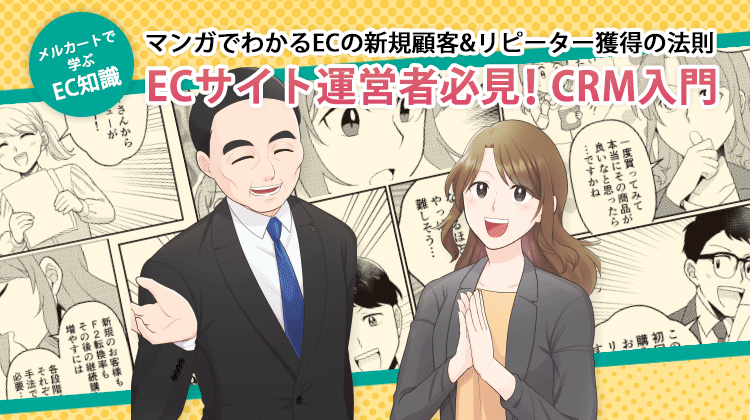
ロイヤルカスタマーとは?
ロイヤルカスタマー(Loyal Customer)とは、ある企業が展開している商品やサービス、あるいは企業そのものやブランドに対して高い「ロイヤルティー(Loyalty)」、つまり「忠誠心」を持つ顧客のことです。「ロイヤル顧客」とも呼ばれます。
ロイヤルカスタマーの特徴
ロイヤルカスタマーの定義は企業によってさまざまですが、ロイヤルカスタマーの主な特徴として以下を挙げることができます。
- 企業や商品・サービスに愛着を持ち、継続的に商品を購入してくれる
- 価格や利便性などで購買行動が左右されることがなく、競合他社に流れにくい
- 口コミなどで第三者に自社製品を紹介してくれる
- 商品やサービスの品質向上につながるフィードバックを積極的に行う、など
噛み砕けば、ロイヤルカスタマーは「その企業のファン」と呼ぶこともできるでしょう。
とくに、少子高齢化などの問題から国内市場が縮小している昨今、業績を伸ばしていくためには、このロイヤルカスタマーをいかに囲い込むかがカギになるとされています。
ロイヤルカスタマーと優良顧客の違い
購入金額や頻度が高く、売上への貢献度が高い顧客のことを「優良顧客」と呼びます。
ロイヤルカスタマーと似たニュアンスを持っていますが、購入金額が大きい優良顧客がすべてロイヤルカスタマーであるとは限りません。
たとえば、優良顧客のなかには「たまたまセールで安かった」「製品に不満はあるが、契約で止めることができない」「他社への乗り換えが面倒」など、ネガティブな理由で自社製品を購入している可能性もあるでしょう。
優良顧客は、たしかに企業の売上に貢献する存在ではあります。
しかし、競合他社がセールを行った場合や、さらに便利な製品を発見したなど、ふとしたきっかけで自社から離脱する可能性が高いです。
一方、ロイヤルカスタマーは自社の製品やサービスに愛着を持っているため、簡単に他社の商品やサービスへと乗り換えません。
つまり、「企業や商品・サービスに愛着を持っているかどうか」がロイヤルカスタマーと優良顧客の大きな違いだと言えるでしょう。
ロイヤルカスタマーを育成するべき理由
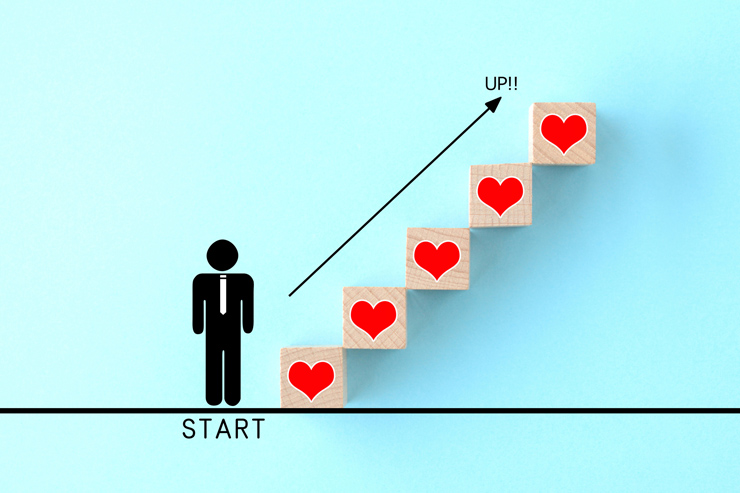
優良顧客とロイヤルカスタマーの違いについて解説しましたが、どちらも売上に貢献してくれることに変わりはありません。しかしなぜ、ロイヤルカスタマーを育成する必要があるのでしょうか。
ここでは、ロイヤルカスタマーが企業にもたらしてくれるメリットの代表例を、より詳しくご紹介します。
売上の安定・向上
先述の通り、ロイヤルカスタマーは長期にわたり繰り返し商品を購入してくれるため、LTV(Life Time Value/顧客生涯価値)の向上が期待できます。
LTVとは、ある顧客が自社や商品・サービスを利用し始めてから終了するまでにもたらす利益の総額のこと。
つまり、ロイヤルカスタマーが増えることで売上が安定しやすくなり、中長期的な売上向上にもつながります。
新規顧客の獲得
ロイヤルカスタマーは第三者に自社のサービスや製品を宣伝してくれる顧客です。
とくにECビジネスにおいては、顧客が自発的に発信する情報、いわゆる「UGC(User Generated Content)」の重要性が高く、企業が発信する情報よりもUGCを購買活動の参考にするという消費者は少なくありません。
ロイヤルカスタマーの育成に取り組むことで、ユーザーが自発的に宣伝・口コミをして商品やサービスを広めてくれるため、広告などの高額なマーケティングコストをかけなくても認知拡大や新規顧客の獲得につなげることができるでしょう。
商品・サービスの品質向上
商品・サービスの品質向上という面でも、ロイヤルカスタマーの存在は重要です。
先述したように、ロイヤルカスタマーは商品・サービスに対して愛着を持ってフィードバックをしてくれることがあります。なかには、商品やサービスをより良くするための改善点や意外な活用方法など、企業側では気づかなかったヒントがあるかもしれません。
こうしたロイヤルカスタマーのフィードバックを参考にすることで、商品・サービスの品質向上につなげることができるでしょう。
リピート購入を増やしたい方は必見!
マンガでわかるECサイトリピーター獲得の法則!
ECサイトでリピーターを獲得するための法則をわかりやすく解説したマンガです。
こんな人におすすめ
・ファン・リピーターを増やしたい
・広告費をかけずに売り上げUPをしたい
・顧客管理システムってなに?
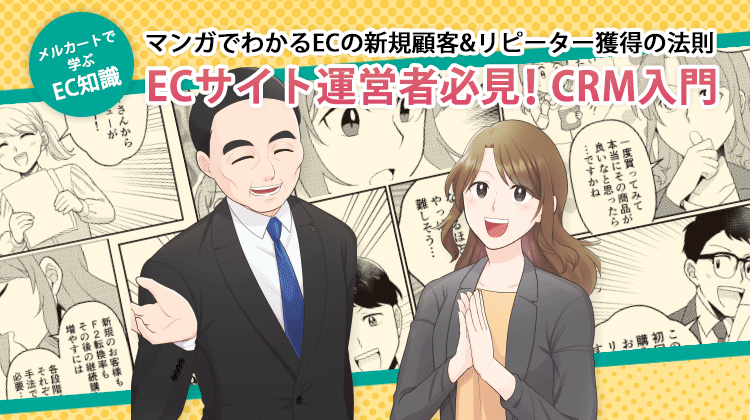
顧客ロイヤルティの分析方法

ロイヤルカスタマーを増やすためにはさまざまな施策を行う必要がありますが、まずは既存顧客が自社に対してどれだけのロイヤルティを抱いているかを分析することが重要です。
分析結果をもとに顧客をいくつかのセグメントに分類し、それに応じてアプローチを仕掛けることで、顧客ロイヤルティの構築に向けた効果的な施策が可能になります。
顧客ロイヤルティの分析方法にはいくつか種類がありますが、ここでは代表的な分析方法をご紹介します。
RFM分析
RFM分析は、Recency (最終購入日)、Frequency(購入頻度)、Monetary (購入金額ボリューム)の3つの指標から顧客をランク付けする手法です。
これら3つの指標をもとに、顧客を「優良顧客」、「見込み客」「離反客」「新規顧客」などのセグメントに分類し、それぞれに応じたアプローチを行います。これにより、効率的に顧客をロイヤルカスタマーへと育成することが可能です。
CPM分析
CPMとは「Customer Portfolio Management」の略で、顧客ポートフォリオマネジメントとも呼ばれます。RFM分析の3要素に、「顧客の在籍期間」も加えてセグメントの分類を行う手法です。
CPM分析は4つの要素から顧客を10個のセグメントに分類し、それぞれにアプローチを行います。RFM分析だけでは十分なアプローチが行えなかった顧客層に対しても、効果的な施策が可能になる点がメリットです。
NPSの活用
NPS(Net Promoter Score)は、顧客が企業にどれくらい愛着や信頼を持っているか判断するための指標です。
「あるサービスを第三者に勧めるかどうか」という質問に、0~10点の間で答えてもらい、0~6点は「批判者」、7~8点は「中立者」、9~10点を「推奨者」として分類します。これにより、実態に即した顧客のロイヤルティを判断できるようになります。
また、LTVの高低とNPSの3分類を組み合わせれば、顧客をより詳細に分類することも可能です。
ロイヤルカスタマーの育成方法

分析した顧客情報を基にして、どのような戦略でロイヤルカスタマーを増やしていけば良いのでしょうか。ロイヤルカスタマーを育成するための方法をご紹介します。
CRM
ロイヤルカスタマーの育成を図る上で、CRM(Customer Relationship Management)の取り組みが重要です。
CRMとは日本語で「顧客関係管理」という意味で、顧客と積極的な関係構築を図り、信頼感を生み出すためのマネジメント手法です。
購買データから年齢や性別、地域などを軸に顧客を分類し、それに応じてダイレクトメールなどでアプローチを仕掛ける方法などもCRMの一例といえます。
ただし、顧客との関係構築を図るCRMは、短期的に成果が出る戦略ではありません。長期的な施策を行い、継続的に顧客と信頼関係を築き上げる必要があります。
CEM
CEM(Customer Experience Management)という戦略も考えられるでしょう。顧客経験価値管理などと訳され、顧客により良い経験を提供して、ロイヤルティを高めていく方法です。
CEMはCRMと異なり、顧客に「思いがけないサプライズ的な経験」を提供することで、顧客の中に眠っていたニーズを引き出すことで信頼感や愛着を高めていきます。
MA
MA(Marketing Automation)とは、個々の顧客と長期的な関係を構築するために使うプラットフォームのことです。
見込み客を育てて購買行動につなげるために使われる場合が多く、CRMなどと連携させて活用すると、より効果を発揮します。
ロイヤルカスタマー育成のポイント
CRMやCEMなどを踏まえたうえで、ロイヤルカスタマーを育成していく際のポイントをいくつかご紹介します。
対象となるペルソナを見定める
ロイヤルカスタマーの育成には長期的な戦略が必要です。また、どれくらいの購買頻度の顧客をロイヤルカスタマーと呼ぶのかは企業によって異なります。
そのため、ロイヤルカスタマー育成を行う前に、自社にとって誰がロイヤルカスタマーなのか、どの顧客がロイヤルカスタマーになりやすいのかなどを見定めることが大切です。
そのうえで、顧客の行動パターンを可視化する「カスタマージャーニーマップ」や、人物モデルとなる「ペルソナ」を設定し、顧客の行動予測からマーケティングを行うようにしましょう。
アンバサダー手法でファンを増やす
アンバサダーとは「大使」という意味を持つ言葉で、「企業と一緒にサービスの普及に努める顧客」のことを指します。例えば、「無料で製品を使える代わりに、SNSなどで口コミをお願いする」といった方法がアンバサダー手法の一例です。
アンバサダー手法を活用することで、投稿者の履歴や投稿についたコメントなどから、顧客の商品に対する熱量やユーザーの反応を知ることもできます。また、顧客からファンを生み出し、ファンに更なる顧客を呼び込んでもらうことも狙えるでしょう。
マーケティングツールを活用する
より効率的にロイヤルカスタマーの育成を行いたい場合は、マーケティングツールを活用するのも一案です。
O2O(Online to Offline)アプリやオウンドメディア、SNSなどを活用すれば、リピーターとコミュニケーションを取り信頼関係を強化する、見込み客を店舗やサイトに案内するといった施策も可能です。
ロイヤルカスタマー育成に強いECサイト構築なら「メルカート」
ここまでは、ロイヤルカスタマーの基本的な知識や育成のポイントを解説してきました。
次は、ロイヤルカスタマーの育成に強いクラウドECプラットフォーム「メルカート」をご紹介します。
「メルカート」は、EC構築20年超の実績を誇る国産ECパッケージ「ecbeing」から生まれたサービスで、クラウドならではのリーズナブルな料金で「ecbeing」の標準機能をご利用いただけます。
では、「メルカート」がロイヤルカスタマーの育成に適している理由を見ていきましょう。
充実の分析機能
「メルカート」には、ロイヤルカスタマーの育成に役立つ顧客分析機能が備わっています。
先述したRFM分析をはじめとした高度な顧客分析機能を搭載しているほか、購入分析も詳細に行うことができます。
これらの分析機能を組み合わせることで、顧客の属性や行動傾向を把握することができ、ロイヤルカスタマー育成に向けた施策につなげることができるでしょう。
ファン化に役立つ機能も豊富
「メルカート」には、分析機能だけでなく、ファン化に役立つ各種機能が豊富に備わっています。
たとえば、各種属性でセグメント分けやステップメール配信などのCRM機能が充実しているほか、定期購入やリピート購入などの幅広い購入方法への対応や、会員ランク機能やポイント機能などもご利用いただけます。
また、初心者の方でも使いやすいCMSを備えているのでページを簡単に追加・更新することができ、ユーザーのファン化を後押しするような情報発信も手軽に行えます。
マイクロサービス利用でさらに便利に
「メルカート」は、ロイヤルカスタマーの育成に役立つマイクロサービスとスムーズに連携できます。
たとえば、当社グループ企業が提供するツール「 visumo(ビジュモ) 」を使えば、InstagramやX(旧 Twitter)と簡単に連携することができ、SNSで発生したUGCをECサイトに掲載することができます。
同じく、当社グループ企業が提供するツール「 ReviCo(レビコ) 」では、メールから最短2クリックで簡単にレビュー投稿できます。
これらのマイクロサービスと連携することで、UGCの活用やレビューの収集を効率的に行うことが可能になり、ロイヤルカスタマーの育成にもつなげることができるでしょう。
ロイヤルカスタマー育成に「メルカート」を活用している事例
最後に、ロイヤルカスタマーの育成に「メルカート」を活用している企業の事例をご紹介します。
顧客との双方向コミュニケーションを活発化(AGCテクノグラス株式会社)
耐熱ガラスの食器ブランド「iwaki」を展開するAGCテクノグラス株式会社は、メルカートを採用して自社ECサイトを構築し、顧客との双方向のコミュニケーションを活発化させることに成功しています。
メルカートでの自社ECサイト構築以前、同社のブランドサイトはスマートフォンに未対応で、社内でサイト更新を行えなかったこともあり、サイトを訪れてくれた「iwaki」のファンを十分におもてなしできていない状況でした。
また、モール型プラットフォームにも出店していたものの、データドリブンの観点でのマーケティング強化に課題を感じていました。
そこで同社は、お客様との双方向コミュニケーションの活発化や情報収集力の強化を図り、ECサイトの立ち上げを決定。
サービス選定では、データ収集・分析に関する機能が豊富で、PDCAを回しながらスピード感を持って運営できる点、そしてマーケティング面を含むサポートの充実度を評価し、「メルカート」でのECサイト構築に至りました。
公式オンラインショップのオープン後、Webサイト更新のハードルが解消され、スピード感を持ったサイト運営が可能に。さらに、サイトでの積極的な情報発信や「visumo」との連携により、お客様との双方向のコミュニケーションが活発化。
メルカートでの情報収集・分析やSNSでのUGCを活用しつつ、顧客のLTV向上に取り組んでいます。
自社ECサイトを起点としたファンマーケティングを展開(株式会社タチバナ産業)
段ボールやプラスチック段ボールの生産・販売、オリジナルブランドの紅茶販売等を手掛ける株式会社タチバナ産業は、メルカートで自社ECサイトをオープンしました。
2015年からECモールへの出店を開始し、紅茶や段ボールなどの自社製品を販売していた同社。
しかし、集客にはつながるものの、さまざまなコストがかかるだけでなく、モール内での検索順位の変動リスクやレギュレーションの制約などが課題となっていました。
そこで同社は、自社でマーケティングやブランディングに取り組み、ファンを育成しながら収益力を高めていくために、自社ECサイトの構築を検討開始。
複数のシステム比較検討し、同社のEC事業規模や予算にマッチしていて、操作性や機能の豊富さ、広告・マーケティングの展開力や将来性、サポートの充実度を考慮した結果、「メルカート」の導入に至りました。
「メルカート」のサポートを受けつつ自社ECサイト「だんぼーる本舗」のオープン後が完了した今、同社では自社製品のブランディングやファンマーケティングに取り組んでいます。
まとめ
今回は、ロイヤルカスタマーの意味や重要性、育成のポイントなどを紹介しました。
企業が売上の安定化や中長期的な成長を図る上で、ロイヤルカスタマーの存在は非常に大切です。
とくにEC領域においては、リピート率の向上やUGCの観点で、ロイヤルカスタマーの育成は重要な取り組みだと言えるでしょう。
ロイヤルカスタマーの育成に課題を感じている企業は、今回ご紹介した「メルカート」でのEC構築・リニューアルをぜひご検討ください。
リピート購入を増やしたい方は必見!
マンガでわかるECサイトリピーター獲得の法則!
ECサイトでリピーターを獲得するための法則をわかりやすく解説したマンガです。
こんな人におすすめ
・ファン・リピーターを増やしたい
・広告費をかけずに売り上げUPをしたい
・顧客管理システムってなに?
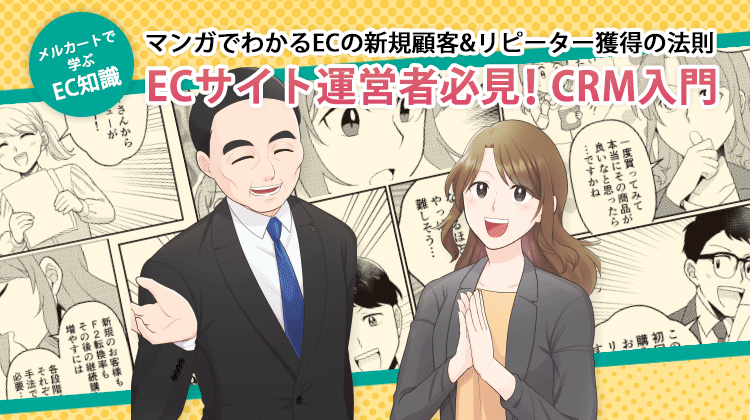
構築・運用・サポート
売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ
成功のノウハウを集めた
実例集プレゼント!
デモも
受付中
この記事の監修者
株式会社エートゥジェイマーケティング責任者座間 保
2007年に㈱エートゥジェイの創業に参画し2009年に独立。マス媒体以外のトリプルメディアを活用した一貫性のあるWeb戦略立案・戦術プランニング・実行・分析・改善に携わる。結果を重視した戦略的なECサイトやオウンドメディア構築を行う。WebメディアやWeb関連事業の起業を3度経験した、シリアルアントレプレナー。2017年に㈱エートゥジェイに出戻り、マーケティング部門を統括している。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします