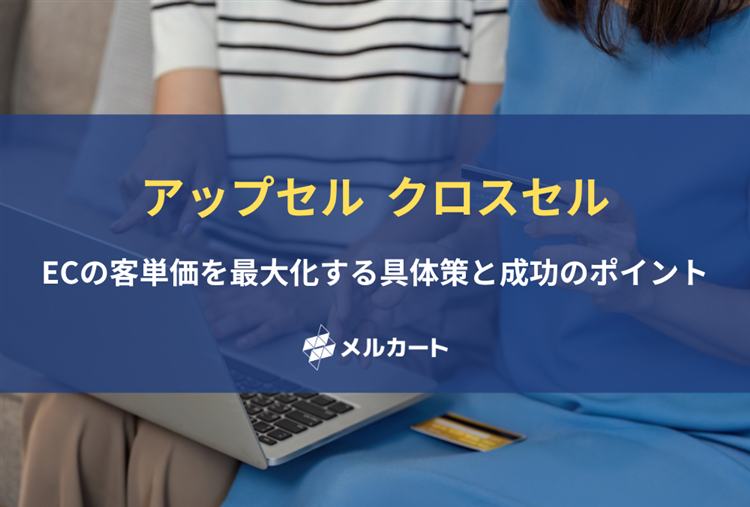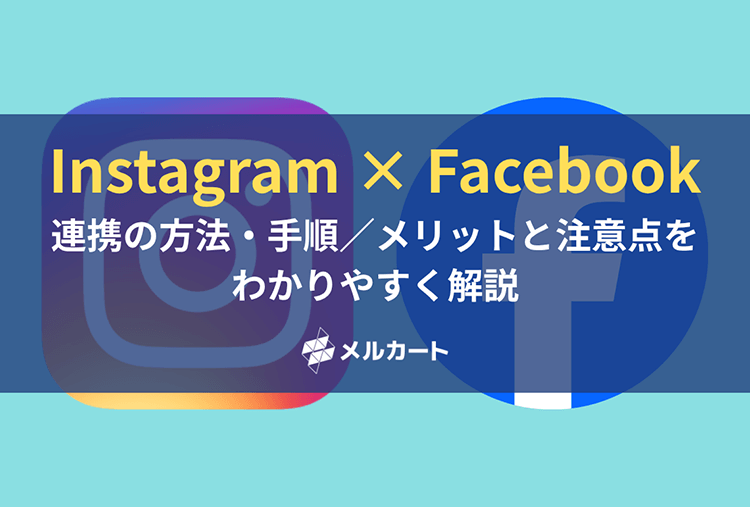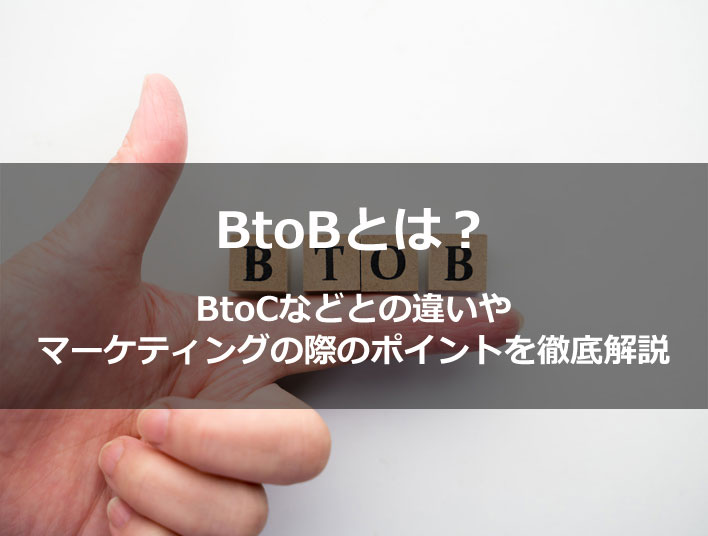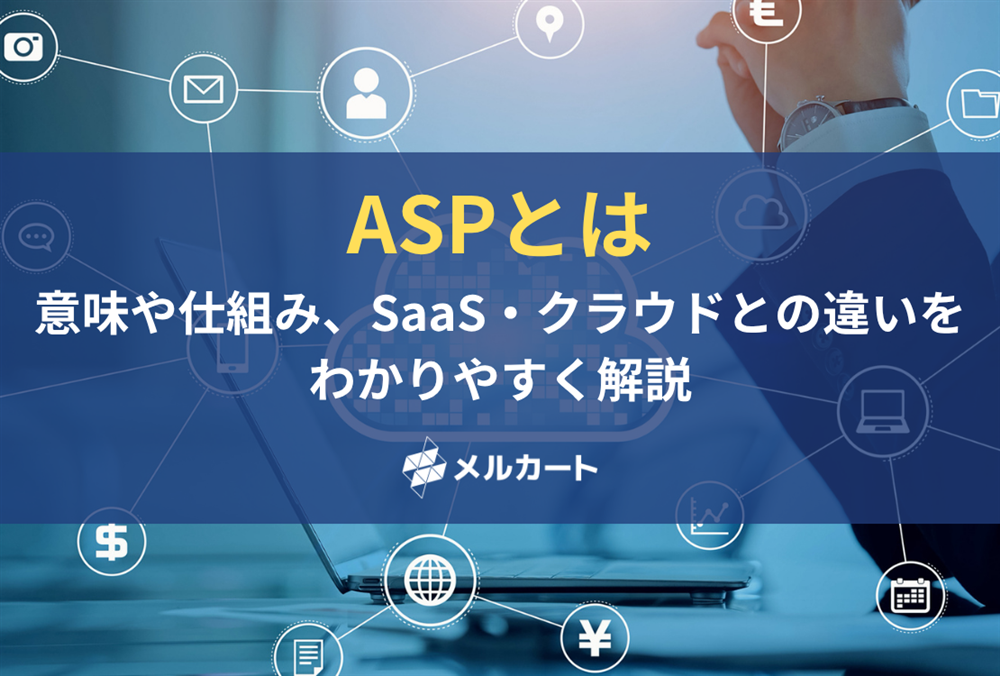EC情報メディア詳細
かご落ちとは?かご落ち率の計算方法や発生原因、改善に向けた対策を解説

ECサイトを運営する上で、「カートに商品は入るものの、購入まで至らない」という課題に直面している担当者の方は多いのではないでしょうか。この「あと一歩」の取りこぼしが、いわゆる「かご落ち」です。
本記事では、ECサイトの売上向上に不可欠な「かご落ち」の意味やかご落ち率の計算方法、かご落ちを防ぐための対策についてわかりやすく解説します。
かご落ち対策をはじめ、売上アップに役立つ機能が充実しているECカートも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【お役立ち資料】「売り上げ規模TOP10企業が行う共通施策108選」を無料ダウンロードする
【目次】
・まとめ
かご落ちとは?EC担当者が知っておきたい基礎知識

まずは基礎知識として、かご落ちの意味を紹介するとともに、かご落ち率の計算方法や平均値、その重要性について解説します。
そもそも「かご落ち」とは?
かご落ちとは、ユーザーがECサイトで商品をショッピングカート(買い物カゴ)に入れたにもかかわらず、購入手続きを完了せずにサイトから離脱してしまうことを指します。かご落ちと同じ意味合いで「カート放棄」と表現することもあります。
カートに商品を入れるという行動は、ユーザーがその商品に対して購入意欲を持っている証拠です。それにもかかわらず最終的な購入に至らないのは、購入プロセスの過程に何らかの障壁や問題が潜んでいる可能性が高いことを示唆しています。
このことから、売上の成長を目指すには、かご落ち防止の取り組みは必要不可欠だと言えるでしょう。
かご落ち率の計算方法は?
自社のECサイトのかご落ち状況を把握するために、まずは「かご落ち率」を算出しましょう。
かご落ち率は、以下の計算式で求めることができます。
かご落ち率(%)=(1−購入完了数/ショッピングカート投入数)×100
たとえば、1ヶ月に1,000件のカート投入があり、そのうち実際に購入まで至ったのが300件だった場合、かご落ち率は以下のようになります。
(1−300/1000)×100=70%
この場合、カートに商品を入れたユーザーの7割が、購入せずに離脱していることになります。
導入しているカートシステムの機能や、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを利用することで、これらの数値データを計測することが可能です。まずは自社のかご落ち率を算出し、現状を把握することから始めましょう。
ECサイトの平均的なかご落ち率の目安
算出した自社のかご落ち率が、高いのか低いのか判断が難しいという方もいらっしゃるでしょう。
世界中のECサイトのUX調査を行うデンマークの調査機関「Baymard Institute」が実施した調査によれば、ECサイト全体におけるかご落ち率の平均は約70%だとされています。
※参照元:49 Cart Abandonment Rate Statistics 2025 – Cart & Checkout – Baymard Institute
また、かご落ち率は取り扱う商材によっても変動し、とくに高価格帯の商材は比較検討に時間がかかるため、かご落ち率が高くなりやすいと考えられています。
約70%という数字はあくまで目安ではありますが、自社のかご落ち率が目安を大幅に上回っている場合、サイト内に改善すべき課題が潜んでいる可能性は高いと言えるでしょう。
かご落ち対策の重要性
かご落ち対策が重要視される理由は、売上アップを目指すうえで費用対効果が高い施策だからです。
基本的にECサイトの売上は以下のような計算式で表されます。
「ECサイトの売上」=「アクセス数(集客)」×「コンバージョン率(CVR)」×「客単価」
かご落ち対策は主に「コンバージョン率(CVR)」に関係する施策ですが、コンバージョン率向上を目的とした各種施策のなかでも成果に直結しやすい取り組みだと言えます。
かご落ちユーザーは、コンバージョンの一歩手前まで来たものの、何らかの理由でサイトから離脱してしまったユーザーです。離脱の原因を特定して取り除くことさえできれば、そのままコンバージョンする可能性は非常に高いと言えるでしょう。
つまりかご落ち対策は、最小限のコストでコンバージョン率を直接的に高め、売上アップに直結する重要な取り組みなのです。さらに、購入プロセスのストレスをなくすことは、顧客体験(CX)の向上にも繋がり、リピート購入の促進や顧客ロイヤルティの醸成にも貢献します。
【お役立ち資料】「売り上げ規模TOP10企業が行う共通施策108選」を無料ダウンロードする
かご落ちを引き起こす8つの原因

次は、かご落ちが発生してしまう代表的な8つの原因について見ていきましょう。
原因1:送料・手数料など追加費用の表示
購入手続きの最終段階で、送料や手数料など想定外の費用が追加されることは、かご落ちが発生する主な原因の一つです。
事前に表示された商品価格に納得してカートに入れたにも関わらず、決済直前に追加費用を提示されれば、ユーザーは「騙された」「送料無料だと思っていたのに」といったネガティブな感情を抱き、購入意欲は大きく削がれてしまうでしょう。
原因2:購入プロセスが複雑・わかりにくい
購入完了までのステップが多すぎたり、次何をすればよいのか直感的にわからなかったりすると、ユーザーは面倒に感じて途中で諦めてしまいます。
たとえば、以下のようなサイト構成は、ユーザーに不要なストレスを与え、離脱の引き金となります。
- 購入完了までのページ遷移が5ステップ以上ある
- 「次へ」ボタンがどこにあるかわかりにくい
- パンくずリストがなく、今どの段階にいるか不明
原因3:入力フォームの項目が多すぎる
個人情報や配送先を入力するフォームの項目が多すぎることも、ユーザーの負担を増やし、かご落ちにつながります。
とくに、購入に直接関係のない情報の入力を求められると、ユーザーは手間だと感じるだけでなく、個人情報の提供に不安を覚えることもあります。このような入力フォームの最適化(EFO:Entry Form Optimization)が未対策であることは、かご落ちを招き大きな機会損失となり得ます。
原因4:商品購入に会員登録が必須
購入にあたり会員登録が必須になっている場合も、かご落ちが発生しやすいと言えます。ECサイトを利用するユーザーのなかには、「この商品を買うためだけに、わざわざ会員登録したくない」と感じるユーザーは少なくありません。
とくに、初めてそのサイトを利用するユーザーにとって、購入前に個人情報を入力してIDとパスワードを設定する作業は、決して低くないハードルだと言えます。
原因5:希望する決済方法がない
ユーザーが利用したい決済方法が用意されていないことも、かご落ちの直接的な原因になります。
近年では、コンビニ払いや後払い決済、ID決済、キャリア決済といった多様なニーズが存在します。
ターゲット顧客が普段利用しているであろう決済手段に対応していない場合、購入をあきらめてしまう原因となり得るでしょう。
※関連記事:ECにおける決済とは?主な決済方法やおすすめのサービスを紹介!
原因6:サイトの表示速度が遅い
ページの表示速度が遅いECサイトも、かご落ちが発生しやすいと言えます。
ページの読み込みが遅いサイトは、ユーザーに大きなストレスを与えます。たとえばGoogleの調査では、ページの読み込みに3秒以上かかると、半数以上のユーザーが離脱するというデータもあります。
原因7:サイトが信頼性に欠ける
サイト全体のデザインが古い、情報が更新されていない、SSL化されていないといった状況は、ユーザーに不信感を抱かせます。
セキュリティへの不安は、個人情報や決済情報の入力をためらわせる大きな要因であり、かご落ちの原因となり得るでしょう。
※関連記事:ECサイトはセキュリティ対策が重要!その理由や対策方法とは?
原因8:何らかの事情で購入を保留している
これまでの原因とは異なり、ユーザーの事情で購入に至っていないケースもあります。
たとえば、以下のような状況が考えられます。
- 他サイトの商品と比較するため、一時的にカートに入れている
- 後でじっくり検討するために、ブックマーク代わりに利用している
- 給料日など、購入するタイミングを待っている
このようなパターンに対しては、サイト改善とは別のアプローチで再訪を促し、購入を後押しする施策が有効となります。
かご落ち率を改善する具体的な対策11選

次は、かご落ちを防ぎ、コンバージョン率(CVR)を改善するための具体的な対策を見ていきましょう。
対策1:入力フォームを最適化(EFO)する
かご落ち対策として有効な施策のひとつが、入力フォームの最適化(EFO)です。
ユーザーの入力負担を軽減することで、購入直前での離脱を防ぎ、コンバージョン率を高めることが可能です。具体的には、以下のような取り組みが有効です。
- 入力項目を最小限にする: 購入に不要な項目は削除する
- 住所自動入力機能の導入: 郵便番号を入力すると住所が自動で反映されるようにする
- エラーのリアルタイム表示: 入力ミスがあった場合、エラー箇所と内容をリアルタイムに表示する
- 必須項目を明確にする: 「必須」「任意」のラベルを分かりやすく表示する
対策2:決済方法の選択肢を増やす
決済方法の選択肢を増やすことも、有効なかご落ち対策です。ユーザーが希望する決済方法を選べるようにすることで、機会損失を防ぐことができます。
クレジットカード決済や銀行振り込み、代金引換といった基本的な決済方法はもちろん、コンビニ決済や後払い決裁、各種ID決済(Amazon Pay、楽天ペイ、PayPayなど)、キャリア決済など、ターゲット層の特性に合わせて、導入する決済手段を検討しましょう。
※お知らせ:クラウドECサイト構築プラットフォーム「メルカート」、90%を占める多彩な決済サービスをカバー
対策3:送料や手数料を事前に明示する
かご落ちを防ぐには、送料や手数料などを明確に、できるだけ早い段階で提示することも大切です。
たとえば、商品ページやカート画面に送料ルール(「全国一律〇〇円」「1万円以上で送料無料」など)を明記したり、カート投入後すぐに送料・手数料を含む合計金額を表示したりといった改善が有効です。
対策4:ゲスト購入に対応にする
「今すぐ買いたい」というユーザーのニーズに応えるため、会員登録をしなくても購入できる「ゲスト購入」の選択肢を用意するのも有効です。
会員登録のメリット(ポイント付与、次回からの入力省略など)は別途伝えつつ、購入完了後に改めて登録を促すのがスムーズな流れです。
対策5:カゴの中身を分かりやすく表示する
かご落ち対策として、ユーザーがカートの中身を正確に把握でき、なおかつ簡単に操作できるようにしましょう。
たとえば、以下のような改善によりかご落ち防止が期待できます。
- 商品画像や商品名、単価、数量、小計を一覧で分かりやすく表示する
- カート画面で、数量の変更や商品の削除が簡単に行えるようにする
- 「買い物を続ける」と「支払いに進む」のCTAボタンをわかりやすく配置する
など
対策6:セキュリティや信頼性を示す
ユーザーが安心して個人情報や決済情報を入力できる環境を整えます。
具体的には、サイト全体のURLを常時SSL対応させたり、プライバシーマークや第三者機関によるセキュリティ認証マークをサイトのフッターなどに表示したりといった対策がサイトの信頼性向上につながります。
対策7:かご落ちメールを配信する
かご落ちメールの配信も有効です。
カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに対し、一定時間後に「お買い忘れはございませんか?」といった内容のメールを自動で送信する手法です。
ユーザーの記憶が新しいうちにリマインドすることで、購入を後押しする効果が期待できます。
対策8:Web接客ツールで購入を後押しする
Web接客ツールを利用し、ユーザーにアプローチするのも有効です。
たとえば、疑問解消に役立つチャットを表示したり、ポップアップクーポンを表示したりすることで、購入を後押しできる可能性があります。
対策9:リターゲティング広告で再検討を促す
リターゲティング広告で購入を後押しするのも一策です。
リターゲティング広告は、一度サイトを訪れたユーザーに対して配信する広告タイプ。リターゲティング広告を目にすることで、かご落ちアイテムの存在を思い出し、商品購入を再検討するきっかけとなります。
※関連記事:ECサイトの集客に役立つ7つのWeb広告を解説!運用のポイントや成功事例も紹介!
対策10:分析機能やツールを活用しPDCAを回す
かご落ち対策は、一度実施したからと言って終わりではありません。
利用しているカートシステムの機能やアクセス解析ツールを活用し、どのページで購入プロセスから離脱しているユーザーが多いのか、ボトルネックとなっている離脱ポイントを定期的に分析しましょう。
データに基づいて仮説を立て(Plan)、対策を実行し(Do)、結果を検証し(Check)、改善を重ねる(Action)というPDCAサイクルを回し続けることが、継続的な売上向上につながります。
※関連記事:ECサイトの分析方法は?売上アップに向けたデータ活用の手順や成功事例を解説!
対策11:かご落ち対策が可能なECカートを導入する
場合によっては、かご落ち対策に有効な機能が充実したECカートに乗り換えるのも手です。
これまで紹介したEFOやかご落ちメールの配信、多様な決済対応といった機能は、個別にツール・サービスを導入するとコストも手間もかかりまってしまいます。一方で、高機能なECカートシステムには、これらのかご落ち対策機能が標準搭載されている場合があります。
現在利用しているカートシステムではかご落ち対策を十分に行えないという場合には、カートシステムの乗り換えも選択肢に加えてみましょう。
かご落ち対策もOK!売上アップを目指すなら「メルカート」
次は、ここまでご紹介したようなかご落ち対策を含め、さまざまな施策を実現可能なECカートとして、「メルカート」をご紹介します。
さまざまな施策を実現する多彩な機能
「メルカート」は、国内ECサイト構築実績No.1のECパッケージ「ecbeing」から生まれたクラウドECプラットフォーム。
「ecbeing」の豊富な標準機能はそのままにSaaS化しているので、集客から販促、リピーター・ファン獲得まで、さまざまな施策を実現可能。
たとえば、ユーザーが購入フロー中のどの画面で離脱したのかを分析できる「かご落ち分析」や、会員登録なしで商品を購入できる「ゲスト購入」、多彩な決済手段への対応、かご落ちユーザーに向けたメール配信を可能にする「CART RECOVERY」連携など、かご落ち対策として有効な機能が豊富に備わっています。
【お役立ち資料】「メルカートの機能資料」を無料ダウンロードする
手厚いサポートで売上アップを目指せる
「メルカート」は、EC初心者でも安心のサポート体制を整えています。
サイト構築・リニューアル段階でのサポートはもちろんですが、リリース後も専任のカスタマーサクセスチームが伴走サポート。
機能の使い方に関する質問から売上アップに向けた相談まで、お客様に寄り添い対応します。また、Web広告運用やコンテンツ制作、CRM支援などのサポートメニューも用意しているので、EC運営やマーケティングに関する知見や社内リソースに不安がある場合でも、安心して売上アップを目指すことが可能です。
「メルカート」によるかご落ち対策の実践事例
最後に、「メルカート」の機能でかご落ち対策を実践した事例をご紹介します。
リンガーハットグループの一角として外販事業を担うリンガーフーズ株式会社は、利用していたシステムのサービス終了を機に、「メルカート」によるECサイトのリニューアルを実施しました。
リニューアル当初から顧客分析に取り組んできた同社ですが、なかでも重用した機能のひとつが「かご落ち分析」でした。かご落ち分析を実施することでユーザーがどの工程で離脱しているのかが明確になり、的確な対策を講じることが可能に。
データに基づく施策の立案・実行により、単月の売上昨年対比で最大215%を達成するなど、大きな成果につながっています。
まとめ
今回は、ECサイトの売上を大きく左右する「かご落ち」に焦点を当て、基本的な知識から対策まで解説しました。
かご落ちはコンバージョン直前での取りこぼしであり、改善することで売上アップにつなげることが可能です。
ECサイトのかご落ちに課題を感じている方は、今回ご紹介した情報も参考に対策を講じてみてはいかがでしょうか。また、記事内でご紹介した「メルカート」は、かご落ち対策を含むさまざまな施策を実現する高機能なクラウドECプラットフォームです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
【お役立ち資料】「売り上げ規模TOP10企業が行う共通施策108選」を無料ダウンロードする
構築・運用・サポート
売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ
成功のノウハウを集めた
実例集プレゼント!
デモも
受付中
この記事の監修者
株式会社エートゥジェイマーケティング責任者座間 保
2007年に㈱エートゥジェイの創業に参画し2009年に独立。マス媒体以外のトリプルメディアを活用した一貫性のあるWeb戦略立案・戦術プランニング・実行・分析・改善に携わる。結果を重視した戦略的なECサイトやオウンドメディア構築を行う。WebメディアやWeb関連事業の起業を3度経験した、シリアルアントレプレナー。2017年に㈱エートゥジェイに出戻り、マーケティング部門を統括している。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします