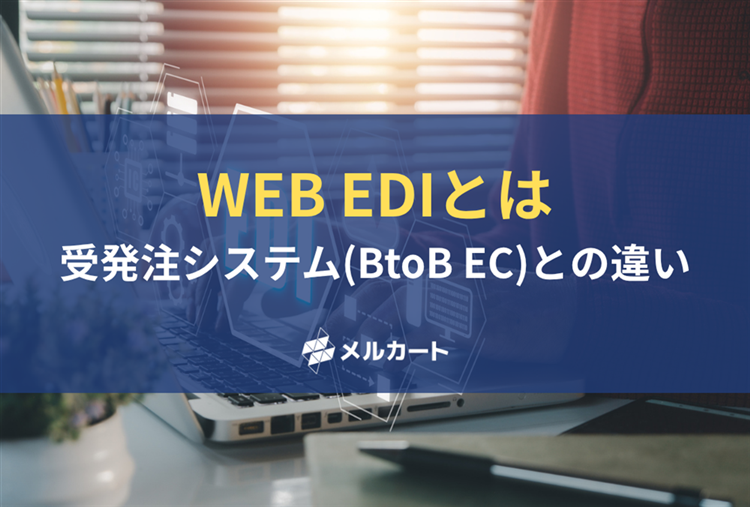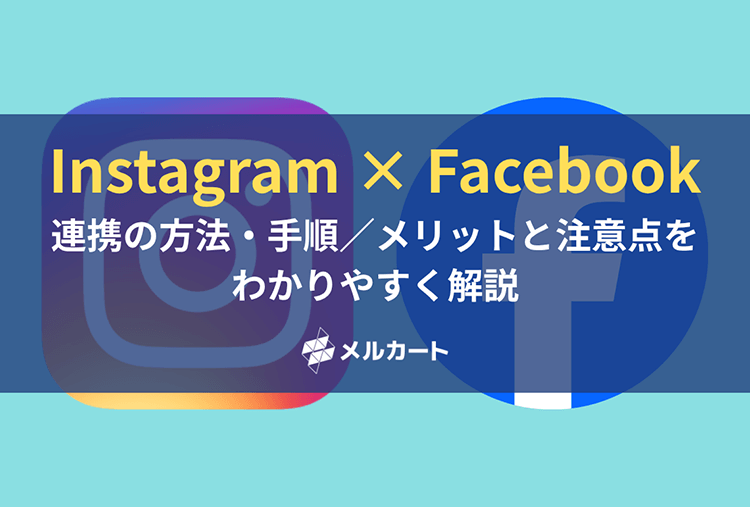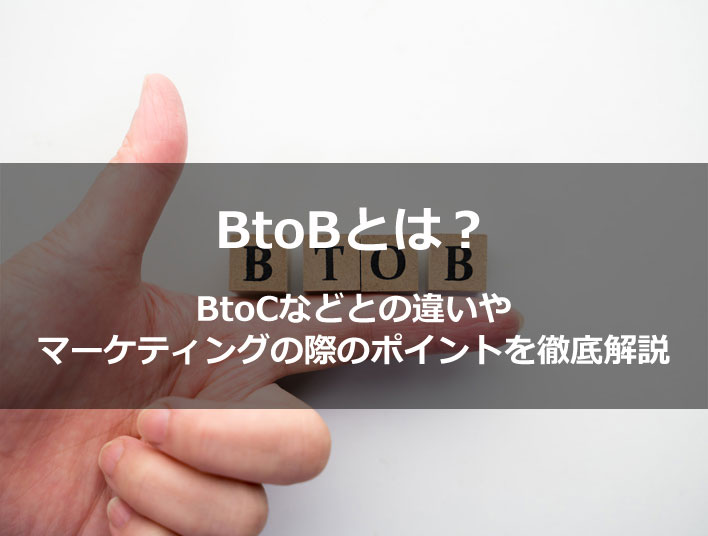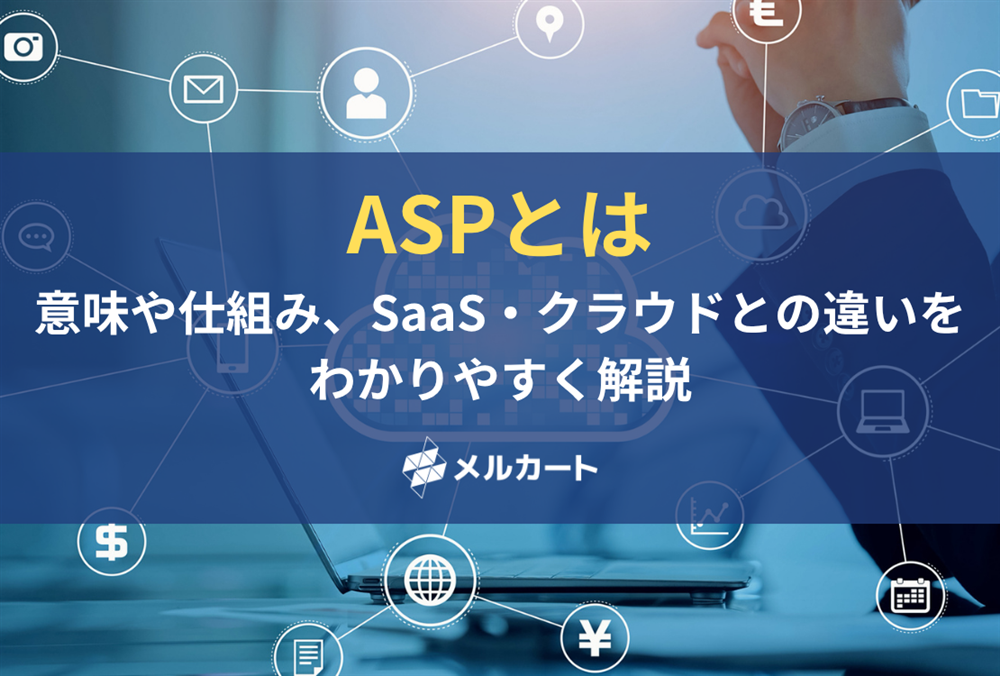EC情報メディア詳細
WEB-EDIとは?受発注システム(BtoB EC)との違いを解説
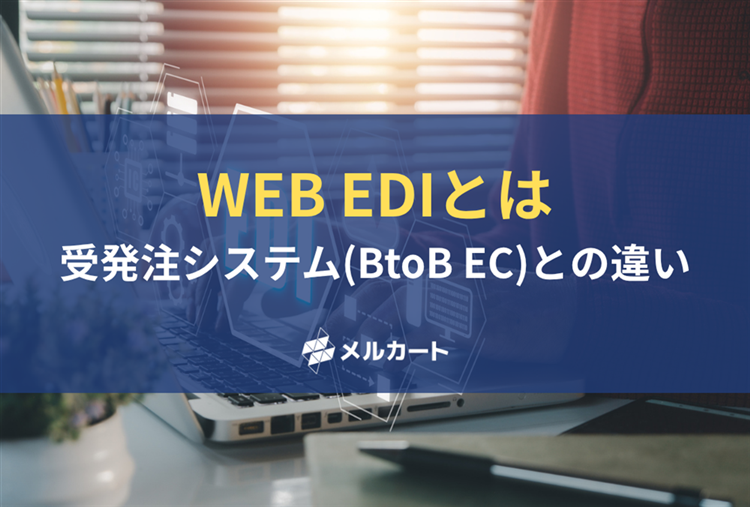
企業間の受発注業務において、効率化とコスト削減が求められる今、「WEB-EDI(ウェブイーディーアイ)」の導入が注目されています。従来のEDIに比べて、インターネット環境があれば手軽に始められる点が大きな魅力です。
本記事では、WEB-EDIの基本から導入メリット・デメリット、さらにBtoB ECの活用方法まで、企業が業務改革を進めるうえで知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
【お役立ち資料】「売り上げ規模TOP10企業が行う共通施策108選」を無料ダウンロードする
WEB-EDIとは
WEB-EDI(Web Electronic Data Interchange)とは、企業間での受発注や納品、請求などの取引データを、インターネットを通じてWebブラウザ上でやり取りできる仕組みです。
従来の専用回線や専用ソフトを必要とするEDIに比べて、WEB-EDIはインターネットとWebブラウザさえあれば利用できるため、導入や運用のコストを抑えながら取引の電子化を実現できます。
中小企業でも導入しやすく、業務効率化やヒューマンエラーの防止といった効果が期待されています。
WEB-EDIの仕組み
WEB-EDIの仕組みは非常にシンプルです。取引先企業が提供するWEB-EDIシステムにログインし、Webブラウザ上で受発注データや納品情報、請求書などを入力・確認・送信することで、リアルタイムに情報が共有されます。
多くのシステムでは、CSVやExcelデータのアップロード・ダウンロードにも対応しており、基幹システムとの連携も可能です。これにより、紙やFAXを用いた従来の取引と比べて、大幅な業務の効率化とスピードアップを図ることができます。
WEB-EDIとEDIとの違い
WEB-EDIと従来型のEDIとの最大の違いは、「通信手段」と「システムの柔軟性」にあります。従来のEDIは、専用回線や専用ソフトを必要とし、初期投資や運用コストが高くなりがちでした。
一方、WEB-EDIはインターネットとWebブラウザを利用するため、導入が比較的容易で、費用も抑えられます。また、従来型EDIが高いセキュリティと安定性を誇る一方で、WEB-EDIは利便性や拡張性の面で優れており、特に中小企業や取引先が多岐にわたる企業にとって有用です。
WEB-EDIとインターネットEDIとの違い
WEB-EDIとインターネットEDIは、どちらもインターネットを活用した取引データの交換手段ですが、利用方法に違いがあります。インターネットEDIは、取引データを専用フォーマットで作成・送信するもので、自社の基幹システムと連携して自動でデータをやり取りすることが多いです。
これに対しWEB-EDIは、ユーザーがWebブラウザ上で直接操作・入力する形で取引を行うのが特徴です。そのため、WEB-EDIはシステム構築の手間が少なく、少量取引やスポット的なやり取りにも向いています。
WEB-EDIのメリット
WEB-EDIは、従来のEDIや紙・FAXベースの業務に比べて、数多くのメリットがあります。中小企業でも導入しやすく、短期間で効果を実感できる点も特徴です。
以下では、それぞれのメリットを詳しく解説します。
コスト削減
WEB-EDIは、従来型EDIに比べて初期費用や運用コストを大幅に抑えることができます。専用回線や専用ソフトの導入が不要であり、Webブラウザがあれば取引を開始できるため、サーバー設置やインフラ整備にかかる費用が不要です。
また、紙の伝票やFAX送信にかかる印刷・通信費、人的工数の削減にもつながり、トータルでのコストパフォーマンスに優れたソリューションといえます。
効率化
紙やFAXを使った手作業での入力・確認作業は、多くの時間と労力を要します。WEB-EDIを導入すれば、受発注や納品、請求などのやり取りがオンライン上で完結するため、入力ミスや確認漏れのリスクを減らせます。
また、履歴管理やデータ検索も容易で、業務のトレーサビリティが高まり、社内業務全体の生産性向上にもつながります。
リアルタイム性
WEB-EDIでは、情報の送受信が即時に反映されるため、リアルタイムでの情報共有が可能になります。これにより、発注状況や納品スケジュールのズレ、在庫の過不足などを素早く把握し、スピーディーな意思決定が可能になります。
特に多拠点や複数取引先との連携が必要な企業にとって、リアルタイム性は業務リスクの低減と競争力強化に直結します。
WEB-EDIを導入する際の注意点
WEB-EDIは利便性が高く、多くのメリットがありますが、導入にあたっては注意すべき点も存在します。
以下に、主な注意点について詳しく解説します。
導入・運用コスト
WEB-EDIは従来のEDIに比べて低コストで導入できるものの、完全に無料というわけではありません。自社の業務フローに合わせたカスタマイズやシステム連携が必要な場合は、初期設定費用や月額利用料が発生します。
また、運用に関しても、操作研修やマニュアル整備、社内外の問い合わせ対応など、人的リソースの確保が必要となる場合があります。費用効果を正確に見積もり、長期的な投資対効果を把握したうえで導入を検討することが重要です。
セキュリティリスク
WEB-EDIはインターネットを介してデータをやり取りするため、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクへの対策が不可欠です。通信の暗号化、アクセス権限の制御、ログ管理など、基本的なセキュリティ機能を備えたシステムを選定することが求められます。
また、社内のセキュリティポリシーと整合性が取れているか、外部からの攻撃に対する備えが十分かなども、導入前に確認しておく必要があります。
取引先の同意が必要
WEB-EDIは自社だけで導入しても効果を発揮しません。実際に取引を行う企業同士が同じ仕組みでデータを共有することが前提となるため、取引先の同意や対応が不可欠です。
特に中小企業では、IT環境が整っていない取引先も存在するため、相手企業の導入ハードルやサポート体制も考慮しながら、段階的な導入計画を立てる必要があります。
場合によっては、複数の取引先との調整が必要になる点も想定しておきましょう。
Web-EDI導入のステップ
Web EDIの導入は、単にシステムを契約して終わりではありません。スムーズに業務へ定着させるためには、導入前の準備、実際の導入プロセス、そして運用・管理体制の構築まで、一連のステップを段階的に進める必要があります。
以下に、それぞれの段階におけるポイントを詳しく解説します。
準備段階
Web EDI導入における最初のステップは、自社の業務課題や取引プロセスの現状を把握することです。受発注・納品・請求など、どの業務を電子化の対象とするかを明確にし、それに応じた要件を整理します。
同時に、取引先のIT環境や協力体制についても確認し、導入対象となる企業との事前調整を行うことが重要です。また、セキュリティ要件や法令遵守の観点から、自社のポリシーと整合性が取れているかも確認しておく必要があります。
導入プロセス
準備が整ったら、具体的な導入プロセスに進みます。まずは、選定したWeb EDIサービスのベンダーと連携し、初期設定やアカウント作成、必要に応じたカスタマイズを行います。
次に、社内の関係部門や取引先と連携してテスト運用を実施し、システムの動作確認や業務フローとの整合性を確認します。
必要であれば操作マニュアルの整備や、社内外への教育・説明会を実施して、現場の理解とスムーズな移行を促進します。
運用と管理
本番稼働後は、継続的な運用と管理体制の構築が重要となります。日常業務でのトラブル対応や操作サポートはもちろん、定期的なログ監視やアクセス権の見直し、データバックアップの実施など、セキュリティ面の管理も怠らないようにします。
また、業務の拡大や取引先の増加に伴い、運用ルールや設定内容の見直しが必要になる場合もあります。ベンダーと連携しながら、柔軟に運用体制を調整できるよう備えておくと安心です。
Web受発注システム(BtoB EC)もおすすめ
Web-EDIは、企業間取引の電子化を実現する有効な手段ですが、近年ではさらに利便性と拡張性に優れた「Web受発注システム(BtoB EC)」の導入も注目されています。
BtoB ECは、Web-EDIではカバーしきれない柔軟な取引形態や業務の自動化にも対応できるため、企業規模や業種を問わず多くの企業にとって有力な選択肢となっています。
Web受発注システム(BtoB EC)とは
Web受発注システム、いわゆるBtoB ECとは、企業同士の受発注業務をWeb上で行えるようにしたEC(電子商取引)プラットフォームのことです。発注側は専用のオンラインカタログや注文画面を通じて商品を選び、在庫や価格を確認しながらスムーズに注文できます。
一方、受注側は注文を自動で受け取り、在庫管理や請求処理まで一括で対応可能なシステム設計になっていることが多く、営業・業務部門の生産性を大きく向上させることができます。
Web受発注システム(BtoB EC)とWeb-EDIの違い
BtoB ECとWeb-EDIの大きな違いは、「ユーザーインターフェースの自由度」と「取引プロセスの柔軟性」にあります。Web-EDIは、あらかじめ定められたフォーマットに沿って取引データをやり取りするのが基本で、定型的な業務に向いています。
一方、BtoB ECはWebサイト形式で取引を進めるため、商品検索、価格変動、キャンペーン設定など、より柔軟で多機能な仕組みを提供できます。また、取引先ごとにUIや機能をカスタマイズしやすい点もBtoB ECの強みです。
Web受発注システム(BtoB EC)とWeb-EDIの共通点
Web-EDIとBtoB ECには、共通する目的と効果があります。どちらも「受発注業務の電子化による効率化」と「取引の正確性向上」を目指す仕組みであり、FAXや電話、紙の伝票といったアナログな手段からの脱却を支援します。
さらに、情報の一元管理や業務のスピードアップ、取引履歴の可視化といった点も共通のメリットです。企業の業務環境や取引形態に応じて、いずれかを選択する、あるいは併用することが効果的です。
Web受発注システム(BtoB EC)を導入するなら「メルカート」
メルカートは、システム連携とデータ活用に強みを持つクラウド型ECプラットフォームです。国内ECサイト構築数で業界No.1の実績を持つ「ecbeing」をベースに開発されており、費用を抑えつつ売上向上と拡張性を実現するEC環境を提供します。
UGC活用や動画マーケティング、CRM/CDP強化など、お客様のニーズに応える多彩なマイクロサービスや外部ツールとの連携による機能拡張で、理想のEC運用を実現します。
メルカートについて詳しく知りたい方は以下のURLから資料をダウンロードしてください。
https://mercart.jp/wp-list/detail/dl-overview
まとめ
WEB-EDIは、インターネットとWebブラウザを利用して、企業間の受発注や請求業務を効率化する仕組みです。導入コストの低さやリアルタイム性が強みですが、取引先の同意やセキュリティ対策が必要です。
また、より柔軟な運用が可能なWeb受発注システム(BtoB EC)も選択肢として注目されています。業務内容に応じて、最適なツールを選ぶことが重要です。
構築・運用・サポート
売れ続ける仕組みが作れるECネットショップ制作サービスをお探しの方はメルカートへ
成功のノウハウを集めた
実例集プレゼント!
デモも
受付中
この記事の監修者
株式会社エートゥジェイマーケティング責任者座間 保
2007年に㈱エートゥジェイの創業に参画し2009年に独立。マス媒体以外のトリプルメディアを活用した一貫性のあるWeb戦略立案・戦術プランニング・実行・分析・改善に携わる。結果を重視した戦略的なECサイトやオウンドメディア構築を行う。WebメディアやWeb関連事業の起業を3度経験した、シリアルアントレプレナー。2017年に㈱エートゥジェイに出戻り、マーケティング部門を統括している。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします